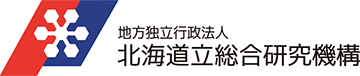道立経営研究成績一覧
- 〈昭和38年〉
| 〔担当場〕 | 道立農試経営部、道立農試北見支場 |
| 〔対象地〕 | 西紋別営農試験地 |
| 〔内容〕 | 道貸トラクター導入の経営効果 |
| 〔担当者〕 | 岩井正敏 |
2.水田経営の規模別採算点-北村構造改善基礎調査結果-
| 〔担当場〕 | 道立農試経営部 |
| 〔共同研究〕 | 北農試農試、北大との共同調査 |
| 〔内容〕 | 損益分岐点分析、自立限界規模 |
| 〔担当者〕 | 不明 |
3.トラクター共同利用方式による経営の変化
| 〔担当場〕 | 道立農試経営部、道立農試北見支場 |
| 〔対象地〕 | 訓子府営農試験地 |
| 〔内容〕 | 道貸トラクター導入による混同経営の確立と土地規模の拡大 |
| 〔担当者〕 | 岩井正敏 |
4.十勝火山灰地帯豆作経営の改善とその成果
| 〔担当場〕 | 道立農試経営部、道立農試十勝支場 |
| 〔対象地〕 | 更別営農試験地 |
| 〔内容〕 | 道貸トラクター導入による豆作経営に乳牛を導入した混同経営の確立 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
5.根釧地方における酪農経営成立の要件に関する調査
| 〔担当場〕 | 道立農試根室支場 |
| 〔内容〕 | 根釧内陸農家の経営形態からみた地域区分とその特徴を明示。 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
6.十勝地域における特異経営-豆単作経営-
| 〔担当場〕 | 北海道立農試十勝支場 |
| 〔内容〕 |
豆作率70%以上の豆単作経営にも拘わらず、タイズシストセンチュウが全く出ていないのは何故か。 しかし、逆にキタネコブセンチュウの生息は著しく、これが豆作の生産を阻害している。 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
7.十勝地方における主要作物動向
| 〔担当場〕 | 道立農試十勝支場 |
| 〔内容〕 | 統計処理、標準偏差、変異計数、回帰分析 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
8.北見地方におけるハッカ機械刈取り方式
| 〔担当場〕 | 道立北見支場 |
| 〔内容〕 | 機械の経済性 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
- 〈昭和39年〉
1.酪農協業経営成立過程の一例
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔内容〕 | 調査研究ではあるが実態の叙述。一般化されていない。 |
| 〔担当者〕 | 岩井正敏、吉野満幸、本庄康二 |
2.駒ヶ岳火山灰地における畑地かんがいの経済性に関する考察
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 駒ヶ岳経営試験農場 |
| 〔内容〕 | かんがい技術の経営的評価であるが、技術的効果は把握されているが、経営経済的評価が十分ではない。しかし、貴重な成果である。 |
| 〔担当者〕 | 宮沢香春 |
3.岩見沢空知丘陵畑作地帯における有畜営農確立に関する経営試験
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 岩見沢営農試験地 |
| 〔内容〕 | 重粘土強酸性土壌地帯における有畜経営の確立 |
| 〔担当者〕 | 宮沢香春 |
4.十勝地方における農業機械の利用状況について
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試農業機械課 |
| 〔内容〕 | 機械利用調査 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
5.別海畑作改善営農試験
| 〔担当場〕 | 道立根釧農試酪農科 |
| 〔対象地〕 | 別海営農試験地 |
| 〔内容〕 | 草地酪農の確立 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
- 〈昭和40年〉
1.てん菜用の機械利用とその経済性
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試農業機械科 |
| 〔対象地〕 | 北海道農業機械実験集落 |
| 〔内容〕 | 畑作機械化農法の確立 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
2.ハッカ省力(機械化)栽培体系に関する試験
| 〔担当場〕 | 道立北見農試作物科 |
| 〔内容〕 | 機械化栽培体系の経済性評価 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
3.共同育雛の実態と問題点
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試経営科 |
| 〔内容〕 | 東川町の共同育雛農家の事例分析 |
| 〔担当者〕 | 工藤晧、黒澤不二男 |
4.集団放牧形態による緬羊飼育の経営方式に関する調査研究
-ラム肥育経営の経済性-
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試経営科 |
| 〔内容〕 | 先進事例調査 |
| 〔担当者〕 | 黒澤不二男、米内山昭和 |
5.士別有畜営農試験地の調査報告
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 士別傾斜地営農試験地 |
| 〔内容〕 | 畜力傾斜地農業の経営転換と基盤整備のあり方 |
| 〔担当者〕 | 長尾正克 |
6.駒ヶ岳山麓における畑地かんがいにともなう営農方式の策定
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 駒ヶ岳経営試験農場 |
| 〔内容〕 | 酪農専業と野菜・酪農複合経営の経営計画策定 |
| 〔担当者〕 | 宮沢香春 |
7.道南高台地における草地酪農確立に関する経営試験
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 瀬棚経営試験農場 |
| 〔内容〕 | 混同経営の成立条件→穀しゅく経営の有畜化 |
| 〔担当者〕 | 宮沢香春 |
- 〈昭和41年〉
1.紋別畑作改善営農に関する試験成績
| 〔担当場〕 | 道立北見農試 |
| 〔対象地〕 | 紋別畑作改善営農試験地 |
| 〔内容〕 | 酪農経営の成立条件 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
2.ばれいしょ用機械試験および調査
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 |
北海道農業機械化実験集落(芽室町中伏古) |
| 〔内容〕 | ポテトディガーとポテトハーベスタの経済性 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
3.大樹町における肉牛経営実態調査
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試 |
| 〔内容〕 | 肉牛経営の確立 |
| 〔担当者〕 | 大沼昭 |
4.共同機械利用における個別経営の対応と展開
| 〔担当場〕 | 道立中央農試 |
| 〔対象地〕 | 美幌町報徳地区のトラクター利用組合 |
| 〔内容〕 | トラクター化による畑作付体系の確立 |
| 〔担当者〕 | 山本毅 |
- 〈昭和42年〉
1.農業機械および施設の経済性とその利用に関する調査
| 〔担当場〕 | 道立中央農試、道立十勝農試、道立新得畜試、道立滝川畜試 |
| 〔対象地〕 | 国貸トラクター利用組合、清水町熊牛北松沢(畑作)、苫小牧市弁天(酪農) |
| 〔内容〕 | トラクター化による経営変動効果の解明 |
| 〔担当者〕 | 長尾正克(代表) |
2.牧草の刈り取り高さと収穫率に関する調査
| 〔担当場〕 | 道立根釧農試 |
| 〔内容〕 | 経済性試算の前提となる技術係数設定の方法開発 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
3.粗飼料(サイレージ)機械化調製体系の可能負担作業量および経済性の試算
| 〔担当場〕 | 道立根釧農試 |
| 〔内容〕 | 牧草サイレージ機械化一貫体系の経営経済的評価 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
4.20馬力トラクターに関する試験
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔内容〕 | 機械化一貫作業体系を設計するための前提となる、各種作業機のほ場走行試験と経済性試算を行った。 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
- 〈昭和43年〉
1.北海道畑作地帯におけるめん羊導入方式に関する研究
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試 |
| 〔内容〕 | 畑作経営におけるめん羊導入の経営的評価 |
| 〔担当者〕 | 米内山昭和、黒澤不二男 |
2.先進的畑作機械化集団に関する試験
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 北海道農業機械化実験集落(芽室町中伏古) |
| 〔内容〕 | トラクターの作業体系の構築、作物別機械利用経費、適正規模 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
- 〈昭和44年〉
1.主要地帯における作付体系別作業体系に関する試験
(1)根釧、天北地帯における草地酪農に関する試験および調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔内容〕 | 飼料の生産技術、機械化省力化面での経営改善を提言 |
| 〔担当者〕 | 金森泰治郎、長尾正克、山本毅 |
(2)主要畑作地帯における作付体系別作業体系に関する試験研究
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 十勝管内芽室町中伏古 |
| 〔内容〕 | 線形計画法の援用による畑作機械化経営の作付体系の設計 |
| 〔担当者〕 | 篠原紀世史 |
(3)斜網畑作地域における作付体系別作業体系に関する考察
| 〔担当場〕 | 道立北見農試 |
| 〔対象地〕 | 網走管内女満別町、小清水町 |
| 〔内容〕 | 線形計画法の援用による畑作経営の作付体系の設計 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
2.大型機械施設の共同利用による畑作経営方式に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 清里町新陽トラクタ利用組合 |
| 〔内容〕 | 経営組織の変化要因、および、機械利用組織の変化要因の解明 |
| 〔担当者〕 | 吉野萬幸、本庄康二、岩井正敏 |
3.北見内陸地域における酪農畑作複合経営の経営分析
| 〔担当場〕 | 道立北見農試 |
| 〔対象地〕 | 線形計画法の援用 |
| 〔内容〕 | 頭数規模に応じた作付体系の選択 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
4.畑作肉牛複合形態における経営計画
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試 |
| 〔内容〕 | 線形計画法の援用による合理的畑作肉牛複合経営の設計 -畑作と肉牛との複合経営の成立条件- |
| 〔担当者〕 | 大沼昭 |
- 〈昭和45年〉
1.麦作団地形成のための大型機械、 施設の運営合理化に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 十勝管内6農協の調査 (芽室町農協、音更農協、士幌町農協、川西農協、大正農協、鹿追町農協) |
| 〔内容〕 | 乾燥施設とコンバインの合理的利用方法の解明 |
| 〔担当者〕 | 篠原紀世史 |
2.道央稲作地帯における複合養鶏の経営計画
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試 |
| 〔内容〕 | 線形計画法の援用による水田規模別養鶏部門規模の確定 |
| 〔担当者〕 | 黒澤不二男、渡辺義雄 |
3.畑作経営から酪農経営への展開方式に関する調査成績
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部、道立新得畜試 |
| 〔対象地〕 | 十勝管内鹿追町 |
| 〔内容〕 | 畑作限界地における経営方式の分化要因の解明 |
| 〔担当者〕 | 金森泰治郎、長尾正克、山本 毅 |
4.公共用草地の技術確定のための調査ならびに現地実証試験
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試 |
| 〔対象地〕 | 十勝管内幕別町営乳牛育成牧場 |
| 〔内容〕 | 預託需要の把握と牧場の技術的、経済的問題点を指摘 |
| 〔担当者〕 | 米内山昭和、大沼昭、斉藤恵二 |
- 〈昭和46年〉
1.水田作の省力化に関する経営経済的調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔内容〕 | 大型コンバインの共同化から3ha以下層の脱落、中型技術体系の台頭を予測 |
| 〔担当者〕 | 金子佳弘、金森泰治郎 |
2.協業化に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 長沼町の稲作協業組織を対象 |
| 〔内容〕 | 組織運営の合理化・改善方向の解明…部分共同の限界性を指摘 |
| 〔担当者〕 | 本庄康二 |
3.農業生産構造に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔内容〕 | 機械化の必然性の解明、土地生産力構成要素と機械化体系の相互規定作用の解明、作目選択論理の解明 |
| 〔担当者〕 | 岩井正敏 |
4.畑作集団生産方式に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 全面共同経営の富良野市麓郷の農事組合法人緑豊農場を対象 |
| 〔内容〕 | 出資均等化方式を実施して人間関係の平等化 |
| 〔担当者〕 | 本庄康二、吉野萬幸、岩井正敏 |
5.てん菜酪農経営の成立条件に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部、道立北見農試 |
| 〔内容〕 | 線形計画法の援用によるてん菜酪農経営の成立条件の解明。
てん菜と酪農との間に密接な関係がないので、 乳牛とてん菜とが有利に結合できないことを指摘。 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
6.酪農生産技術の経済性に関する調査
| 〔担当場〕 | 道立根釧農試 |
| 〔内容〕 | 経産牛1頭当たり乳量の向上→農業所得の向上(このシェーマに問題あり)1頭当たり乳量向上の阻害要因→産乳量の季節偏倚→冬期飼料の質的・量的不足 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
7.畑作養豚複合経営における展開過程と成立条件
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試 |
| 〔対象地〕 | 端野町 |
| 〔内容〕 | 複合養豚のメリット・デメリットを所得で判定する。 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄、黒澤不二男 |
- 〈昭和47年〉
1.稲作転換営農に関する調査研究成績
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部、道立北見農試、道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 道央稲作地帯、十勝稲作地帯(音更、池田等)、北見稲作地帯(北見、訓子府、端野等) |
| 〔内容〕 | 水田規模別に専作化(単作化)と複合化の合理性を解明、経営転換の基幹作物は玉ねぎ |
| 〔担当者〕 | 山本 毅、篠原紀世史、前川奨 |
2.畑作農業集団化指標作成
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部、道立北見農試 |
| 〔対象地〕 | 網走管内網走市実豊第20集団を対象 |
| 〔内容〕 | 営農集団活動のための機械化体系とその運営方法の解明 |
| 〔担当者〕 | 前川奨 |
3.やさい作経営の展開に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 大野町と伊達町が対象 |
| 〔内容〕 | 野菜作農家の経営構造の解明 |
| 〔担当者〕 | 吉野萬幸 |
4.酪農経営における投資効率に関する調査
| 〔担当場〕 | 道立根釧農試 |
| 〔対象地〕 | 中標津町の酪農家30戸が対象 |
| 〔内容〕 | 1頭当たりの所得が最終的に農業所得を規定する。 やみくもな規模拡大に警鐘。 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
5.畑酪経営における標準技術体系の実証
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試 |
| 〔対象地〕 | 場内実証試験、実態値で補正。 |
| 〔内容〕 | 技術組立試験。標準技術体系は、酪農に限定。技術の経営的評価。 |
| 〔担当者〕 | 米内山昭和、大沼昭、斉藤恵二 |
6.北海道における和牛子牛市場の実態
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試、道立滝川畜試 |
| 〔内容〕 | 調査市場の買参人の性格解明と市場価格形成の要因解明 |
| 〔担当者〕 | 米内山昭和、黒澤不二男、大沼昭 |
- 〈昭和48年〉
1.畑作経営規模拡大の手順解明に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立北見農試 |
| 〔対象地〕 | 小清水町の1事例の解析 |
| 〔内容〕 | 経営規模拡大の展開手順と条件の解明 |
| 〔担当者〕 | 河野迪夫 |
2.畑作経営の集団化に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部、道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 富良野市の心和農場を対象 |
| 〔内容〕 | 傾斜地の共同経営の成立条件解明。 |
| 〔担当者〕 | 岩井正敏、本庄康二、吉野萬幸、篠原紀世史 |
3.麦作団地形成のための大型機械、施設の運営合理化調査研究
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 芽室町を対象 |
| 〔内容〕 | 乾燥施設の選択問題、半乾貯留施設かダイレクト乾燥機かの選択。半乾貯留施設が有利…豆類、雑穀など他の作物にも使用可 |
| 〔担当者〕 | 篠原紀世史 |
4.大型畜産経営の経営方式に関する調査研究
| 〔担当場〕 | 道立滝川畜試、道立新得畜試 |
| 〔内容〕 | 家族経営の大型酪農経営228戸のアンケート(道内先進事例)。先進経営の到達点は成換頭数で60頭規模 |
| 〔担当者〕 | 黒澤不二男、大沼昭、米内山昭和 |
5.畑酪経営における高度集約技術の確立と標準技術体系の実証に関する試験
| 〔担当場〕 | 道立新得畜試 |
| 〔内容〕 | 実用化技術組立試験の経営経済的評価 |
| 〔担当者〕 | 渡辺義雄 |
- 〈昭和49年〉
1.稲作から経営転換に関する調査研究 -稲作から畑作、酪農への転換-
| 〔担当場〕 | 道立中央農試経営部 |
| 〔対象地〕 | 上川北部(名寄市、士別市)を対象 |
| 〔内容〕 | 転作を契機に水田酪農と田畑作の複合経営に分化しつつあるが、その定着条件として耕地拡大、集約作物の導入を提言。 |
| 〔担当者〕 | 金森泰治郎 |
2.稲作からの経営転換に関する調査研究 -たまねぎ作の団地化に関する調査-
| 〔担当場〕 | 道立北見農試 |
| 〔内容〕 | 共販体制の確立、その前提となる貯蔵庫の建設 |
| 〔担当者〕 | 河野迪夫 |
3.畑作物の生産流通に関する調査研究 -小麦の収穫乾燥施設の運営方式に関する調査研究-
| 〔担当場〕 | 道立十勝農試 |
| 〔対象地〕 | 芽室町 |
| 〔内容〕 | サブ乾燥方式の経済評価。待ち行列を適用。 |
| 〔担当者〕 | 篠原紀世史 |
4.農業経営における投資効率に関する調査研究-草地酪農経営における投資行動パターンについて-
| 〔担当場〕 | 道立中央農試 |
| 〔対象地〕 | 宗谷管内猿払村浅茅野 |
| 〔内容〕 | 投資に対して「積極型」と「消極型」の二パターンがあることを主張。負債バランスで類型区分する方法は、投資=負債とみる点で問題があるという論議であるが、実際には投資的負債とこげつき負債を識別している。 |
| 〔担当者〕 | 長尾正克 |
5.農業経営における投資効率に関する調査研究 -草地酪農地帯における組勘帳簿による経営の簡易診断法について-
| 〔担当者〕 | 道立根釧農試 |
| 〔対象地〕 | 根室管内中標津町 |
| 〔内容〕 | 成換1頭当たり所得は乳代と高い相関関係にあるので、乳代を高めるためには粗飼料の量と質を高めることが経営改善の課題とした。 |
| 〔担当者〕 | 相田隆男 |
 経営分野のホ-ムペ-ジへもどる_
経営分野のホ-ムペ-ジへもどる_