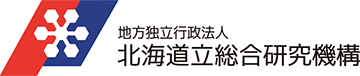研究成果 根釧農試 研究通信 第2号
根釧農試 研究通信 第2号(1993年3月発行)
研究成果
1 乳牛の超音波画像解析による繁殖機能と栄養状況
超音波断層装置による生殖器の診断精度を検討し、分娩後の子宮の継続的な修復状況や卵胞発育状況を詳細に観察しました。また、泌乳初期の栄養充足率が繁殖機能に及ぼす影響を検討しました。
1.超音波断層装置による生殖器の診断精度
超音波断層装置による生殖器の観察では、乳牛に苦痛を与えず、小型卵胞を含めた卵胞数や黄体の内部構造および子宮の修復経過を詳細に観察できます。卵胞は、直径が2mm程度まで判定することができ、10mm以上の卵胞では、摘出した卵巣を直接観察した結果とほとんど差がありません。黄体は周囲の卵巣実質よりエコーレベルの低い台形の画像として得られ、内部に中心腔を持っていますが、腔の多くは次回排卵までに消失します。超音波断層装置による生体内の子宮は、2本の輪郭線に囲まれたエコーレベルの低い円筒形あるいは楕円形として描出されます。生体内での超音波断層像による外側輪郭線は、子宮の血管層を、内側輪郭線は子宮内膜面を表わします。
2.分娩後の排卵間隔とその後の繁殖性
供試牛は、初回排卵から第2回排卵までの排卵間隔により10日以内(5頭)、11日~19日(12頭)、20日~29日(18頭)および30日~40日(5頭)の4群に分けて検討しました。排卵間隔が20日以上と長い牛群では、19日以内の短周期に比べ子宮修復までの日数が増加します(表3)。排卵間隔が10日以内の5頭は、受胎までの日数が57.8日で、排卵間隔が20日以上の牛群(78.3日、77.8日)より有意に短縮されました(P<0.01)。
3.分娩後の栄養充足と卵巣の動態
TDN充足率の毎日の変動パターンにより4つの型に分類し、繁殖能力との関係について検討しました。
Ⅰ型:TDN充足率は分娩後減少し、1週目頃から増加し、10日~20日目に80%を超える小ピークを形成した後再び減少し、30日~40日目に100%程度にまで回復します。卵巣の動態は、TDN充足率の増加に伴い、初めて最大卵胞が形成され、小ピークの前後に初回排卵します。その後、TDN充足率の減少時に2番目の最大卵胞が形成され、7日~10日存続した後退行します。その後、3番目の最大卵胞が発育し、第2回目の排卵をします。
Ⅱ型:分娩後、TDN充足率の減少期間が2週~3週と長く、その後75%~80%の小ピークを形成します。卵巣の動態は、最大卵胞が分娩後TDN充足率の75%以下の時形成され、多くは排卵せず閉鎖退行します。その後、TDN充足率の増加に伴い2番目や3番目の最大卵胞が発育し、初回排卵をします。
Ⅲ型:分娩後、臨床型乳房炎などの疾病などによりTDN充足率の減少が50%以下と大きく、その後の回復により20日頃に小ピークを形成します。卵巣の動態は、小型卵胞の発育はみられるものの最大卵胞の形成は無く、臨床的には卵巣静止の状態です。その後、TDN充足率が80%以上に回復するとともに、初回最大卵胞が形成されます。
Ⅳ型:分娩後の要求量に対しTDN摂取量は常に3kg~5kg不足し、TDN充足率の小ピークが無く、65%~80%の範囲で変動します。その間、卵巣の動態は、複数の最大卵胞が形成されるものの排卵せず、閉鎖退行を繰り返します。
4. 変動パターンの型と繁殖成績
変動パターンの型と繁殖成績では、初回排卵までの日数がⅠ型で15.9日と最も短く、Ⅳ型で47.7日と最も長くなっています。初回排卵までの最大卵胞数か多いほど、排卵までの日数が長く、特に初回排卵の遅延するⅣ型では最大卵胞数が3.3個と多くなっています。最終的に、Ⅰ型およびⅡ型では受胎率がそれぞれ90.2%、100%と、ほとんど受胎しますが、Ⅲ型およびⅥ型では受胎率がそれぞれ50.0%、60.0%と不受胎が多く、また、Ⅳ型では受胎までの日数が120.0日と長くなっています(表4)。
5.まとめ
①TDN充足率の回復が早い牛は受胎性も高いのですが、TDN充足率の回復が遅い牛は受胎性が悪いので、TDN摂取量を大きくする工夫が必要です。
②分娩時、難産や起立不能など異常がある場合、あるいは乳房炎や蹄病に罹患した場合など、栄養以外のストレスなどの要因も分娩後の繁殖機能の回復に影響するので注意が必要です。また、分娩後、子宮や卵巣機能が速やかに回復するよう、とりわけ、食い込みの悪い牛について、適切な栄養充足率となる飼養技術の確立が望まれます。
表1 卵胞数と最大卵胞の直径
|
生体 |
摘出 |
薄切卵胞数 |
||
|
処理 |
2 ~ 4mm |
14.5 |
16.0 |
16.0 |
|
5 ~ 9mm |
4.0 |
4.0 |
3.8 |
|
|
10 ~ 14mm |
0.8 |
1.3 |
1.0 |
|
|
15mm ~ |
1.0 |
1.0 |
1.0 |
|
|
最大卵胞直径( mm) |
16.8 |
13.3 |
16.3 |
|
表2 子宮頸管と子宮角中央部の断面積 断面横(c㎡)
|
頚管 |
左角 |
右角 |
||
|
生体内子宮の超音波画像 |
外側輪郭線 |
7.9 |
5.8 |
5.1 |
|
内側輪郭線 |
4.6 |
3.3 |
3.1 |
|
|
摘出子宮の超音波画像 |
外側輪郭線 |
9.2 |
8.2 |
|
|
中間輪郭線 |
6.7 |
5.6 |
5.7 |
|
|
内側輪郭線 |
3.6 |
3.1 |
3.1 |
|
|
摘出子宮 |
最外層 |
9.3 |
8.5 |
|
|
円形の血管層 |
7.4 |
5.8 |
4.9 |
|
|
子宮内膜面 |
2.9 |
2.9 |
3.1 |
|
表3 初回排卵から第2回排卵までの間隔で4群に分けた半群のその後の繁殖性
|
例数 |
初回~第2回間隔 |
P1)のピークng/ml |
子宮回復日数 |
受胎日数 |
|
5 |
810 |
4.7 |
41.4 |
57.8A |
|
12 |
1119 |
5.8 |
38.2a |
72.7 |
|
18 |
2029 |
6.8 |
42.5b |
78.3 |
|
5 |
3040 |
5.8 |
45.6b |
77.8B |
|
平均 |
6.5 |
41.5 |
74.0 |
注)大文字P<0.01、小文字P<0.05、1)黄体ホルモン
表4 TDN充足率で4型に分けた初回排卵前の最大卵とその後の繁殖性(受胎牛の成績)
| TDN充足率型 |
例数 |
受胎数 |
受胎率 |
受胎日数 |
最大卵胞数 |
排卵初回 |
日数第2回 |
|
Ⅰ |
29 |
28 |
96.6 |
90.2 |
1.1 |
15.9 |
39.3 |
|
Ⅱ |
5 |
5 |
100.0 |
74.8 |
2.2 |
26.8 |
47.8 |
|
Ⅲ |
8 |
4 |
50.0 |
75.5 |
2.3 |
36.3 |
58.1 |
|
Ⅳ |
5 |
3 |
60.0 |
120.0 |
3.3 |
47.7 |
84.7 |