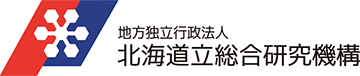エンジュヒメハマキ Cydia trasias
写真1 虫糞の塊。札幌、イヌエンジュ。2010/8/5。 |
写真2 幼虫(?終齢)、体長11mm。写真1と同じ個体群。2010/8/5。 |
写真3 幼虫(?亜終齢)。写真1と同じ個体群。2010/8/5。 |
| 樹種 | イヌエンジュ、エンジュ。 |
| 部位 | 枝先・芽・葉柄の内部。 |
| 時期 | ほぼ通年。 |
| 状態 | 葉がしおれて落下し、葉柄内に食べ痕や虫糞がある。 枝先が枯れる。枯れた部分の根元付近に糸でつづられた虫糞が付く。そこに穴があり、枝の内部にトンネルがある。トンネル内に幼虫・蛹・蛹殻がみられる。 |
| 幼虫 | 体長最大約10mm。胸腹部は黄白色、淡い褐色の斑紋がある。頭部は淡い茶色。 |
| 蛹 | 体長約7mm。黄褐色。 |
和名 エンジュヒメハマキ(文献1984)
学名 命名者・年 Cydia trasias (Meyrick, 1928) (文献1984)
分類 チョウ目(鱗翅目)Lepidoptera、ハマキガ科Tortricidae
分布 北海道・本州、クナシリ島、中国(文献1984)。
文献1984において日本から初めて報告された。標本は北海道で1962年、本州で1967年以降に採集されている(文献1984参照)。
形態 成虫・蛹・幼虫の形態は文献1984に詳述されている。
生態 宿主はエンジュ、シダレエンジュ、イヌエンジュ(文献1984)。
本州では成虫は年2回、4~5月と7~8月に発生する(文献1987)。
幼虫は葉柄や芽に穿孔し、これらを食い尽くした後、枝の内部を2~3cm食い進む;穴の入り口は糸でつづられた糞でテントのように覆われる;老熟幼虫のときに枝に潜って越冬する;加害部位の中で蛹になる(文献1984)。中国では蛹化場所が日本と異なるようである(文献1987参照)。
被害と防除 中国ではエンジュやシダレエンジュの重要害虫である(文献1984)。日本では1980年代に本州各地で被害が観察された(文献1984、1987)。しかし、1990年代以降、目立った被害は発生していないようである。
本州では街路樹のエンジュや山中に自生するイヌエンジュにかなりの被害が発生している(文献1984)。イヌエンジュでは造林地でも被害が観察されている(文献1987参照)。
被害を受けると葉はしおれて落下し、枝先が枯死する(文献1984)。植栽間もない幼木の生長阻害と樹形悪化をもたらす(文献1987)。
樹冠に薬剤散布したところ、その後の被害発生は見られない(文献1987)。
文献
[1984] 駒井古実・S. Lantoh, 1984. エンジュおよびイヌエンジュを加害する小蛾エンジュヒメハマキ(新称) Cydia trasias (Meyrick, 1928)について(鱗翅目, ハマキガ科). 蝶と蛾, 35: 145-151.
[1987] 遠田暢男・山崎三郎, 1987. イヌエンジュの新梢害虫エンジュヒメハマキ. 森林防疫, 36: 13-16.